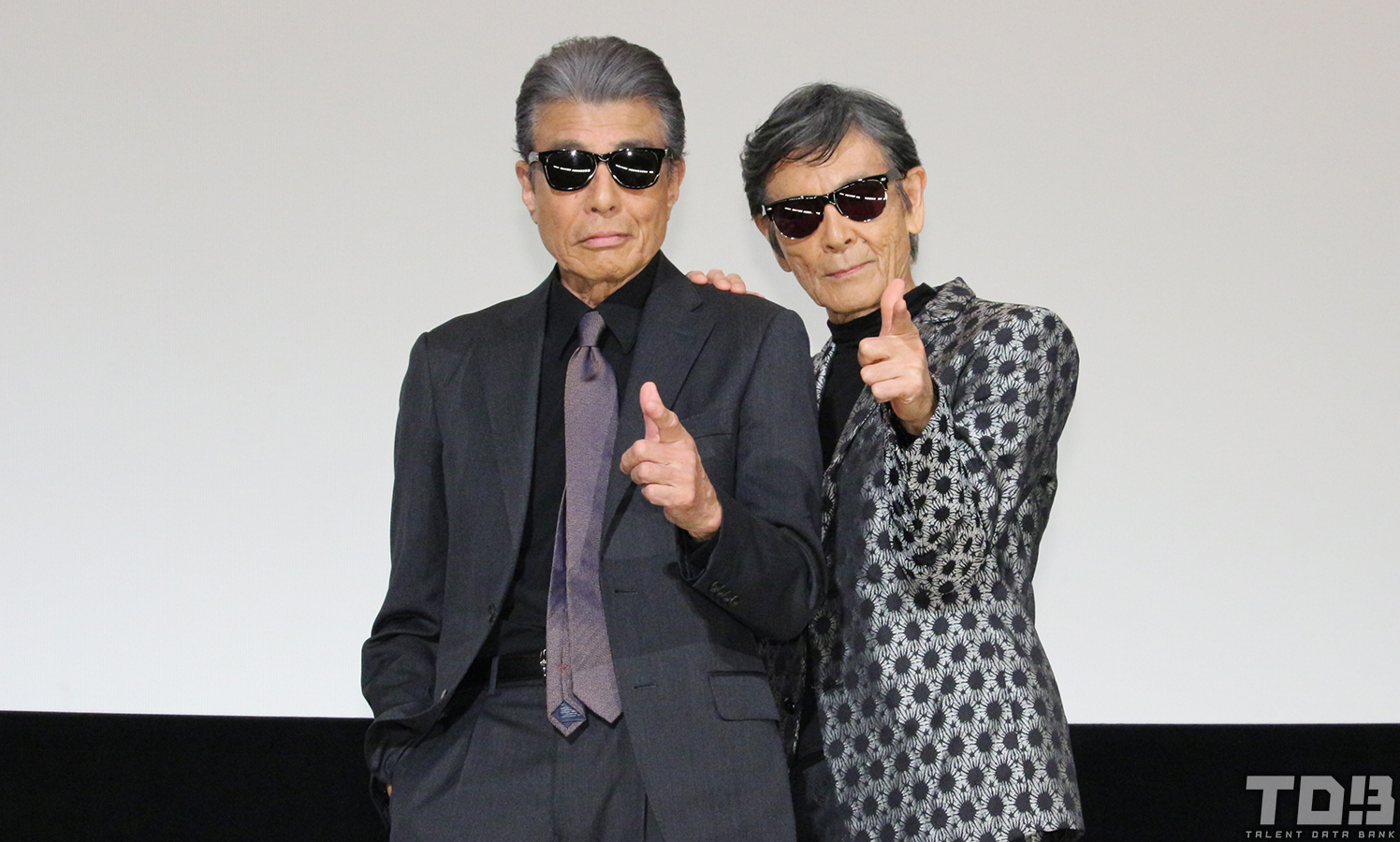この度、一足先に本作を鑑賞し、主人公・沙苗がたどり着いた“愛し方”の結末を体感した10名の豪華著名人、諏訪敦彦、内山拓也、辛酸なめ子、鈴木涼美、石田真澄、絶対に終電を逃さない女、佐々木チワワ、伊藤さとり、門間雄介、松崎健夫より本作のコメントが寄せられた。
【コメント一覧】
<諏訪敦彦(映画監督)>
それが生であれ死であれ、ひとつに溶け合うことが愛だろうか?自ら仕掛けた罠に嵌る危険を顧みず『熱のあとに』が言葉との格闘によって綱渡りのように手繰り寄せるのは、「2」であること。決して融合することのないあなたと私。しかし、その無限の距離にこそ愛は生起する。その驚くべき瞬間を見よ。
<内山拓也(映画監督)>
滂沱のごとく流れる愛に苦しくなった。
愛は哲学であり、思想であり、営みでもある。
127分の中で、愛を掴むために身勝手にも懸命にもがく主人公たちと一緒に、
大切な60秒を知った。
<辛酸なめ子(漫画家・コラムニスト)>
世間一般の恋愛は、この映画の愛に比べたら生ぬるかったようです……
沼落ちどころではないブラックホールに落ちた男女の人間模様から目が離せません。
<鈴木涼美(作家)>
自分の小さな身体の中には到底押し込めきれない感情の熱は一体どこへ向かうのか。受け入れてほしい相手なのか、受け入れてくれそうな相手なのか、それともそのどちらでもないのか、私にはよくわからない。でも決して逸らされない強烈な視線に、あの事件への論理を超えた一つの答えが示された気がした。
<石田真澄(写真家)>
星の数ほど愛の形も、愛の表現方法もある。自分の持つ愛の形にひたすらに向き合い変化に気づいていく沙苗の目が忘れられません。
<絶対に終電を逃さない女(文筆家)>
人々が一口に愛と呼んでいるものは、本当はいろんな形がある。
自分の愛や相手の愛がそれぞれどんな形なのかを考え抜いて向き合う強さと、社会のルールに合わない形の愛を貫く痛みを引き受ける覚悟を持った
一人の女の、愛の語り。
<佐々木チワワ(ライター)>
彼女の愛は鮮烈で眩しい。平凡な生活を愛であると言い聞かせている私たちに、狂気的な愛の信憑性と暴力性をぶつけてくる。その衝動的な愛を、あなたは認めることができますか。
<伊藤さとり(映画パーソナリティ)>
愛に正解はない。
だから共感が良い映画だと思うのは危険。
なぜならば、人の感情にもグラデーションであり
それを他者の視点で知るのが映画なのだ。
そういった意味で、この映画はまさに「愛」の火種。
エネルギーに火傷しそうな愛の映画。
共感できなくて良い。
なのに惹きつけられ忘れられない、愛の姿そのものだった。
<門間雄介(ライター・編集者)>
愛とはすべてを捧げるもの――それは本当に愛なのか?
惑い、ゆらゆらと揺れ、凶暴にのたうつ心のうちを、こんなふうに、こんなにも言語化した日本映画を、他には思いつくことができない。
<松崎健夫(映画評論家)>
この映画は全編がメタファーで構成されている。或る描写や或るモチーフを反復することで暗喩を生み、伏線となってミスリードさせる。だから観客もまた視界不良な行く末に翻弄されてしまうのだ。
併せて、健太(仲野太賀)が沙苗(橋本愛)に結婚指輪を渡す、湖畔での散歩シーンを初解禁!
今回解禁したのは、婚姻届を出した帰り道、湖畔を散歩しながら健太が沙苗の左手の薬指に結婚指輪をはめるシーン。沙苗は指輪のサイズが緩く「ゆるゆる」と優しく笑う。
「ずっと気になってたんだけどさ、それって傷?」と沙苗の左手の傷について尋ねる健太。その傷は沙苗が中学2年生の時、友人に「結婚線がないから家族に恵まれない」と言われたことがきっかけで、沙苗自らの手で彫刻刀で結婚線を作ろうとしてできた傷だという。
「初恋だった佐々木君とどうしても結婚したかったんだよね」「でも結果“イカれすぎ”って振られた」と遠い目で薄っすらとほほ笑みながら語る沙苗。その言葉に吹き出して笑う健太。
「悲劇ってこういうものなんだって初めて思った」と続ける沙苗に、「(結婚線を)彫ったのも無駄じゃなかった」と歩み寄りながら微笑む健太。すると沙苗は健太の肩を優しく叩き「行こ、小泉さん」と手を繋ぎ二人で仲良く歩き出した。
愛したホストを刺し殺そうとした過去をもつ沙苗を、普通の生活へ引き戻してくれる健太の温もりが十分に伝わってくるが、沙苗から明かされる“左手の傷の過去”によって、沙苗の“愛し方”の始まりを伺うこともできる本編映像となっている。