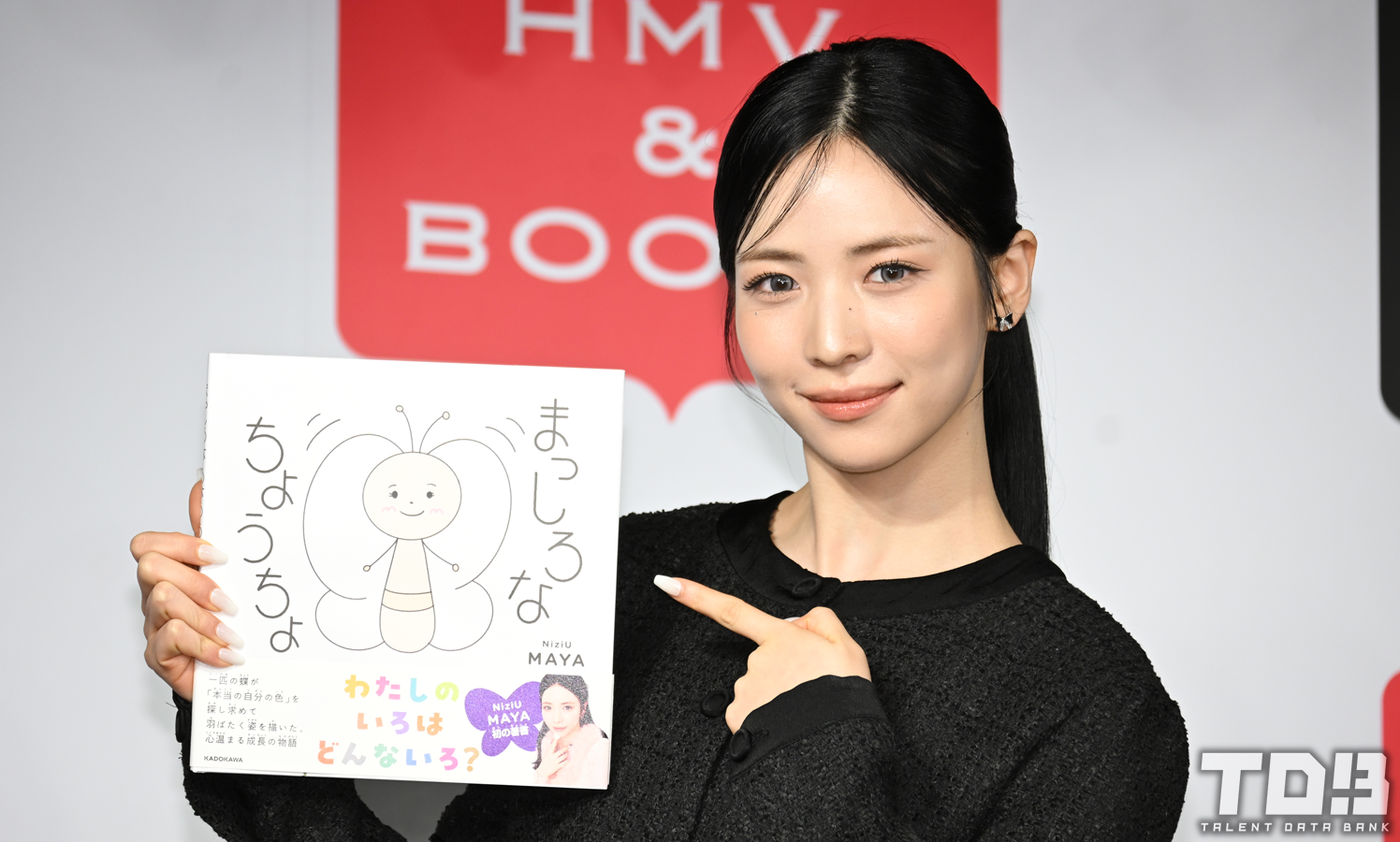※一部本編のストーリーに関わる内容が含まれています。本作未鑑賞の方はご注意ください。
まず初めに松崎氏が、「最も印象に残っているのは、ファーストショット。アイドルを描く時は、ライブシーンから始まるようなイメージがあるが、この作品はアイドルがバックヤードに入っていくところから描くので、『我々はこれからアイドルの世界の裏側を見せてもらうんだ』という気持ちになった。どうやって今作の最初のシーンを構築したのか?」と尋ねると、深田監督は、「バックヤードから描くというのは、最初から決めていた。この映画がある種アイドルの裏と表の両方を見せる映画であるという。普通に見ていたらさりげなく流れていくこのシーンが、実はアイドル業界の方から『リアリティがある』と非常に評判がいい。」とファーストショットに込めた想いを語った。
フランス・パリで行われたイベント『LES SAIZONS HANABI』への参加を終えて、試写会当日の朝、帰国したという深田監督。松崎氏から、多くの映画祭に出品している本作について、海外での評価について問われると、「フランスのカンヌ、韓国の釜山、中国のピンヤオなど、各国の映画祭での上映に立ち合ってきたが、現地のレビューをみていると傾向は全然違う。欧米をはじめとしたアイドル文化の無い国々においては、この作品が描く問題は、ある種、遠い国の社会問題のように感じられる。一方で、日本に住んでいる以上、私たちは、映画、音楽番組、CMなど、あらゆるところにアイドルがいてアイドルと共存してきた。アイドル業界に対する解像度の高さによってこの映画の見え方が異なる。見え方が分かれるということもまた自分の意図したこと。」と述べた。

そして、当日本作を鑑賞した参加者からも質問を募集すると、深田監督へ多くの質問が寄せられた。
「(アイドルの立場で恋愛をする主人公に対して)『間違っているよ』と言葉にして明確に伝える人、理屈を押し付けるキャラクターがいなかった。この構成はあえてなのか?」という質問に対して、深田監督は「本来、大抵の場合はその役割を果たすのは事務所だと思うが、本作では事務所を比較的フラットで、良心的ともとれる存在として描いた。それは本作で描きたいのが、アイドルの主体性の問題だから。事務所を非常に暴力的な悪として描いてしまうと、『この事務所が悪い!』となって、構造の問題に目がいかなくなる。逃げ道を作ることになってしまうのではと考えた。観る人自身の恋愛観やアイドル観をあぶりださすようなものにしたかった。」と回答。
また、「自分も芸能系のことをしていて、事務所に入るときに彼氏がいるかなどを厳しく問われたので共感できるシーンがあった。」と感想を述べた女性が、真衣と敬の結末について真意を訪ねると、深田監督は、「今回の映画の核になるのは『選択』。本作において、白黒つけること以上に、真衣が自分で考えて、自分の意志で主体的に選択することが重要だと思っている。作中の裁判は、実は非常に表面的な裁判。仕事を放棄したから、損害賠償を払えというお金の問題。そこに違和感を覚えた真衣は、『自分は何と戦っているのか?』と自問自答し、裁判所では表に出ない大上段の問題があるのではないかということに気が付く。一方でアイドルではない敬はその違和感に気が付けなかった。そこで溝が生まれてきてしまう。」と語った。
そして時間の許す限り観客からの質問に回答した後、最後には写真撮影タイムが設けられ、本イベントを締めくくった。
さらに、元AKB48・峯岸みなみ、俳優・齊藤工、森崎ウィンといったエンターテインメントに関わる多くの著名人から感想コメント(第二弾)が到着!
<著名人コメント(五十音順)>
■藍染カレン(俳優) ※元ZOC
アイドルってなんだろう。この映画を観てる間ずっと思っていました。
その全てを見ろ、と言われた気持ちでした。
こんなに歪で、危うく美しい”お仕事”を私はアイドルの他に知りません。
アイドルってなんだろう。その輝きに、己に、問い続けるのだと思います。
■宇垣美里(フリーアナウンサー・俳優)
人が人らしく生きていくって、どういうことなのか。
「こうあるべき」に支配され、
どんどん心がその色に染まっていったあの頃を勝手に重ね、流れる涙に溺れそうになった。
それぞれの目線も思いも丁寧に描かれ、
誰のことも断罪しない結末だからこそ、
残された問いの答えをずっと考えている。
■内田也哉子(文筆家・無言館共同館主)
まるでファンタジーのように、
自分と掛け離れた世界の物語かと思いきや、
気づけば、自分の中に渦巻く感情と真理の混沌にゾッとしていた。
これぞまさに深田監督マジック!
■香月孝史(ライター)
私たちがいつしか見慣れてしまった光景の異常さを、静かに浮かび上がらせる。
主人公のいとなみがいとおしいほどに真っ当だからこそ、現実社会の歪みは一層鋭く照射される。
問い続けることを、やめてはいけない。
■齊藤工(俳優)
『恋愛裁判』は、恋愛のかたちを借りながら、
日本社会の「なぜか当たり前になっている違和感」を証言台に立たせるような映画だった。
制度やルール、そして“夢を追う者”が、ごく自然に負担を背負わされていくどこか歪な構造が、
静かに、しかし鋭く浮かび上がってくる。
その違和感を、きちんと“違和感のまま”返してくれる、今の日本でこそ観るべき一作。
■ジャ・ジャンク―(映画監督)
「愛する自由」を訴えるというテーマに強く惹かれた。
アイドルやエンターテインメント産業に一石を投じる、感動の物語だ。
■早川千絵(映画監督)
自分はいったい何と闘っているのか。そんな主人公の声が終始聞こえてくるようだった。
彼女にだけ見えている景色があることを、その静かで強いまなざしが語っていた。
■本間かなみ(テレビ東京ドラマプロデューサー)
生きている。
それを、これほど豊かに雄弁に語るアイドル映画、初めてだった。
自分をコンテンツ化することの矛盾と魔力の中で
息づくシスターフッドが最高に愛おしい!
おいしいご飯をお腹いっぱい食べれますように。
■峯岸みなみ(タレント) ※元AKB48
あのとき語った決意も感謝も、誰にも言えなかった胸の高鳴りも、
全部全部嘘じゃないから苦しいんだ。
走ったり、歩いたり、止まったり、また進んだり…
ハッピーエンドの形はひとつじゃないから、全てのアイドル、
そしてファンの皆様が自分なりのハッピーエンドにたどり着けますように。
※鑑賞は自己責任でお願いします!
■森崎ウィン(俳優)
なんて面白いんだ。
今もなお時代の先頭を走るアイドル文化。そこにこの映画。
深田晃司監督、あなたの世の中を見る視点が、なぜこんなにも天才的に面白いのでしょうか。
ワンカットワンカットに溢れるアイドルの人間模様。
すごくワクワクしました。