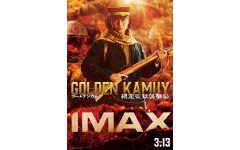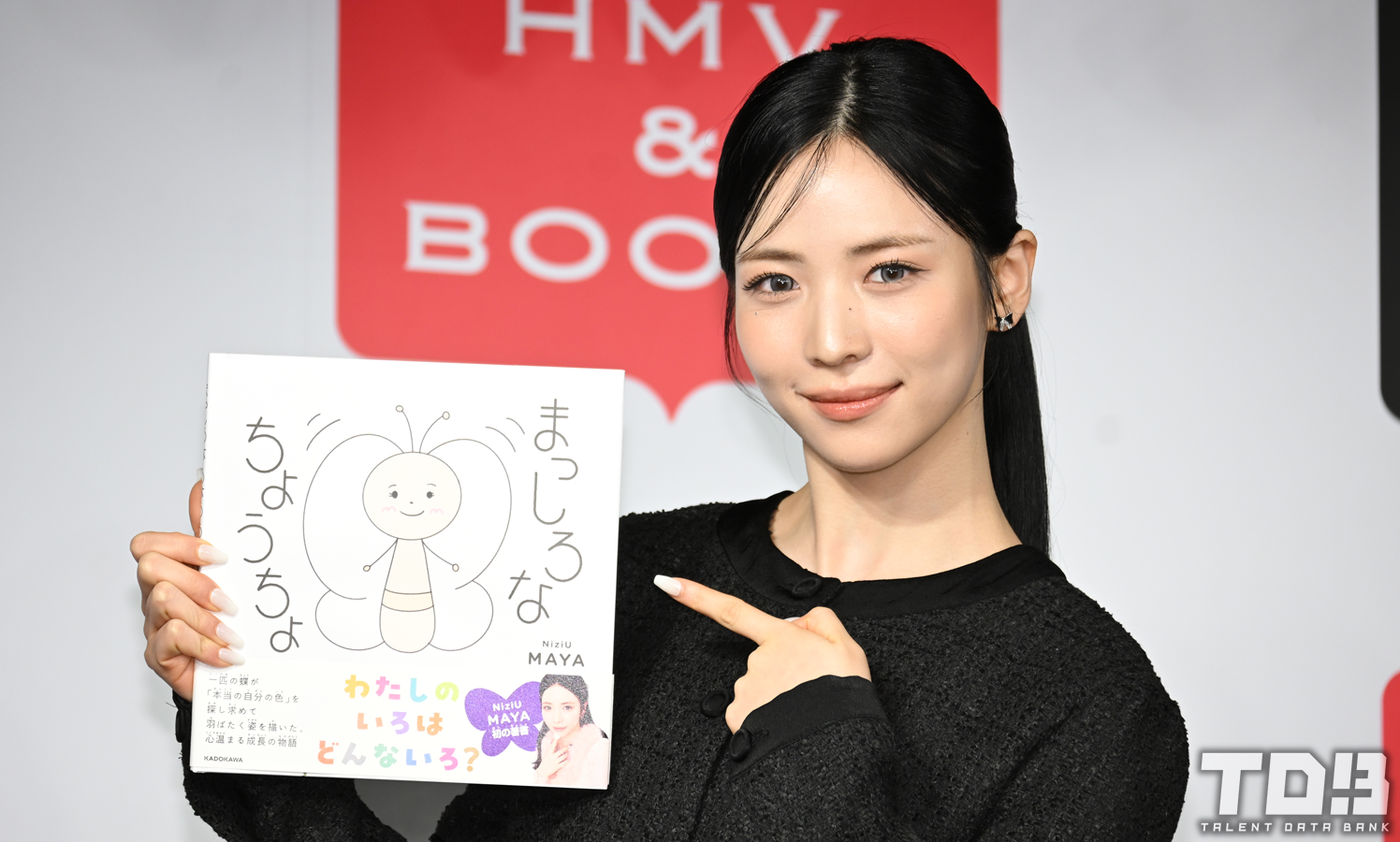アザービジュアル6点がこの度解禁、通常ポスターとは違う縦長仕様の形状で統一されている。希代子・朱里・奈津子・恭子の4人がドレスを纏い見上げる写真では「夢のような時間(とき)だったかもしれないー」のキャッチコピー。ifを感じさせファンタジックな印象の1枚に。
また4人のソロ写真では、希代子(當真あみ)は今までの赤系のカラーとは一変した緑一色の文字色で新たな姿を表現。また朱里(中島セナ)は海外生活のイメージを想像させる唯一の英字タイトルを載せ、希代子と違い、まっすぐな視線を向けた「変わらない青」を打ち出している。奈津子(平澤宏々路)は、中学からの仲良しである希代子との記念写真のようで一見楽しそうな瞬間であるが、「ただ、一緒にいたかっただけなんだ」という意味深な言葉が想像を膨らませる。恭子(南琴奈)は恭子らしいピンクの可愛らしさはあるが、一方で表情はクールな真顔であり彼女の奔放な明るさとはまた違う顔を見せている。
またメイキング映像では、ロケ地である江ノ島付近の海岸の模様や、まだ工事中の下北沢の様子が映し出され、吉田監督と綿密にコミュニケーションを取る様子の希代子(當真あみ)、朱里(中島セナ)の姿が。また下北沢の駅内では、エキストラを多く配置し、「みんなソワソワしている」という言葉も出ているように緊張している雰囲気が伝わってくる。撮影の合間のひと時の表情も映し出され、映画本編のシリアスな部分とはまた違った撮影風景がみられる。
<各界からのコメント ※五十音順・敬称略>
■ISO(ライター)
自信も信念もなく、風が吹けば向きを変える風見鶏。それでも特別でいたくて、隣にいる人に己の価値を見出そうとしてしまう。自分のそんなところが大嫌いだけど変えられない——。集団でいることが当たり前だった学生時代に覚えのある黒い感情を、この痛ましい青春劇はじわじわと呼び覚ます。彼女らの誰のことも好きになれないが、それは彼女らの中にかつての自分の無様さを見るからだ。その憧れも嫉妬も孤独感も全部知っている。与えた傷は、与えられた傷よりも深い痛みとして残り続けることも。
■伊藤亜和(文筆家)
身に覚えがある。自分の輪郭もままならないうち、強いられた庭のなかで生き続けなければなかったこと。憧れの愛で方も知らず、枯らせるばかりだった頃のこと。それぞれがそれぞれに、自らの毒でその身を痛めつけていた。あの苦しみに意味はあっただろうか。もはや記憶とも呼べない欠片が、ときどきほんの一瞬足先をくすぐる。そうか、私はいまだ裸足だったのか。少女たちの笑い声がまだ遠くに聞こえている。私もたしかに、あそこにいた。
■宇垣美里(フリーアナウンサー・俳優)
特別になりたくて、
だから特別な人の特別な人になりたかった。
狭い教室の中が世界の全てだったあの頃。
間違ってばかりの青春は、
繊細なくせに大胆で、
不格好で凶暴で、
身に覚えがありすぎる。
特別になんてなれやしないことを
知ってしまった私は、もう大人なんだろう。
鑑賞後心に直接爪を立てるような痛みが、
ちりりと残ってたまらなかったのは、あの頃には戻れ得ないからこそ。
私たち、なんて残酷だったんだろうね。
■折田侑駿(文筆家)
少女たちの心の機微に焦点を当てた作品は、この世にごまんとある。日本映画だけに絞ってみても、ありとあらゆる角度から語り尽くされてきた。しかし本作はそのどれとも違う。分かりやすく残酷な事件が起こるわけではないし、そうした描写はひとつとしてないように思える。ただ、最初から最後まで恐ろしい。何度も何度も息を呑む。これぞ“演出の映画”なのだ。
■児玉美月(映画批評家)
正反対な少女たちは、出逢った瞬間に違うからこそ猛烈に惹かれ合い、だからこそ反発し合う。
わたしはあなたにはなれないということ。
あなたはわたしにはなれないということ。
その現実をたやすく受けいられないほど曖昧な自他の境界性とともに生きる彼女たちの痛み、
傷つきを、『終点のあの子』は決して多くを語らず、切実な筆致で映像そのものに落とし込んでいる。
篠原哲雄(映画監督)
高校時代。男子校にいた僕は自分が特別な存在であることを常に意識している奴をどこか毛嫌いしていた。自分は客観的に常に平等でいようと努めていた。特別な彼は「お前はいい奴だから」と僕に近づいてきた。僕にはそんな彼が鬱陶しく思える時があったが、極力問題が起きないように振る舞うことも忘れずにいた。こんな事書きながら本作は女子の映画である。つまり本作は性別に関わらず思春期特有の普遍的な人間関係を描いてくれている。女子である分、可愛さと醜さが不可分にも共存し、グロテスクとも言える。画面も生々しく彼女たちに寄り添ったり突き放したり容赦ない。
吉田浩太は、「スノードロップ」も今作も、精神の深い内奥を映画で捉えようとしている。一見表面化出来そうで出来ないことを敢えて映画で捉えること。この冒険はなかなかにスリリングで、この先彼はどこまで深まっていくのだろうという期待を抱かせてくれた。
■菅井友香(俳優)
女子校で青春時代を過ごした私は、
あの頃上手く言葉にできなかった気持ちに触れられ、胸がチクッとしました。
綺麗ではない感情も否定せず、
心情を繊細に描いた本作はとてもリアルで、
自分の色を見つけようとしている方々へのエールのようにも感じました。
個性的な人物が登場しますが、
きっと観る方の年代やタイミングによって、
共感できるキャラクターが変わってくる作品だと思います。
特に文化祭のダンスシーンは圧巻です!
観終わった後、私は過去の自分を少しだけ抱きしめたくなりました。
皆さまもぜひ劇場でご覧ください。
■辻愛沙子(株式会社arca 代表取締役 / クリエイティブディレクター)
「ただ、一緒にいたかっただけなんだ」
たったそれだけのことなのに、
素直に伝えられないことがある。
何歳になっても、人の気持ちは難しい。
この作品を見る人の数だけ、
それぞれの「あの子」の物語がある。
久しぶりに語りたくなる作品に出会えました
■和田彩花(詩と言葉のアーティスト)
瑞々しい棘をもつ青春の物語り。透明感のある映像美と若さの揺らぎのコントラストが光る。
象徴的に何度か繰り返される登場人物たちが撮りあった場面の美しさに後押しされて、私の棘のある青春の思い出をも重ねては、それを美化しそうになった。
青春ってその輝きを肯定する言葉だと思っていたけれど、高校生たちの複雑な心情、言葉が意図せずにいろんな方向へ広がっていくことを見つめ直させてくれる青春の物語りがとても嬉しかった。いつでもきっと友情を問い直せると思わせてくれた。